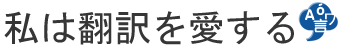- テキスト
- 歴史
คิดถึงคุณเสมอ
คิดถึงคุณเสมอ
0/5000
また柿を一つ箸で摘もうとするが、小さな柿をは嫌々しながらしばらく箸から逃げ回っていた。「千寿郎は優しいから、いつも稽古をつけてもらっている俺には言いにくかったんだろうと思う。兄として不甲斐ないばかりだ」煉獄千寿郎の嘆きは、まるで自分の事を鏡で見ているかのようだった。どう頑張っても埋まらない兄弟との差、どれだけ身を捧げれば得られるか分からない到達点。自分は選ばれていないという絶対的な感覚。弟の話をする彼は、私がこれまで見た彼のどんな表情とも違って見えた。慈しみに溢れ、優しく、しかしどこか不安そうな表情だった。姉が言葉を選ぶ時の顔と同じだった。「正直俺には、死ぬ間際に君に鬼殺隊を辞めろと言った花柱さまの気持ちが痛いほどよく分かる。俺だって、弟が鬼と戦っていると想像すると途端に血が冷たくなる。自分が死ぬよりずっと怖い。しかし、同時に君の気持ちも分かるんだ。俺も父に鬼殺隊を辞めろと何度も言われている。俺には大した才能は無い、どうせ死ぬだけだとな」驚いて顔を上げ、彼を見た。そんな事をこの人に言える人間がいるという事が信じられなかった。彼の父親は現役の炎柱、煉獄槇寿郎だ。「でも俺は諦めたくない。才能があるかどうかは分からないが、それは関係がないと思う。人を助けたいし、鬼のいない世界を作りたいから鬼殺隊を続ける。それだけだ。」
翻訳されて、しばらくお待ちください..
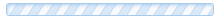
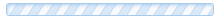
他の言語
翻訳ツールのサポート: アイスランド語, アイルランド語, アゼルバイジャン語, アフリカーンス語, アムハラ語, アラビア語, アルバニア語, アルメニア語, イタリア語, イディッシュ語, イボ語, インドネシア語, ウイグル語, ウェールズ語, ウクライナ語, ウズベク語, ウルドゥ語, エストニア語, エスペラント語, オランダ語, オリヤ語, カザフ語, カタルーニャ語, カンナダ語, ガリシア語, キニヤルワンダ語, キルギス語, ギリシャ語, クメール語, クリンゴン, クルド語, クロアチア語, グジャラト語, コルシカ語, コーサ語, サモア語, ショナ語, シンド語, シンハラ語, ジャワ語, ジョージア(グルジア)語, スウェーデン語, スコットランド ゲール語, スペイン語, スロバキア語, スロベニア語, スワヒリ語, スンダ語, ズールー語, セブアノ語, セルビア語, ソト語, ソマリ語, タイ語, タガログ語, タジク語, タタール語, タミル語, チェコ語, チェワ語, テルグ語, デンマーク語, トルクメン語, トルコ語, ドイツ語, ネパール語, ノルウェー語, ハイチ語, ハウサ語, ハワイ語, ハンガリー語, バスク語, パシュト語, パンジャブ語, ヒンディー語, フィンランド語, フランス語, フリジア語, ブルガリア語, ヘブライ語, ベトナム語, ベラルーシ語, ベンガル語, ペルシャ語, ボスニア語, ポルトガル語, ポーランド語, マオリ語, マケドニア語, マラガシ語, マラヤーラム語, マラーティー語, マルタ語, マレー語, ミャンマー語, モンゴル語, モン語, ヨルバ語, ラオ語, ラテン語, ラトビア語, リトアニア語, ルクセンブルク語, ルーマニア語, ロシア語, 中国語, 日本語, 繁体字中国語, 英語, 言語を検出する, 韓国語, 言語翻訳.
- 神
- 内面も外面も全ての私を愛して
- 私
- La virino ne dormas multe
- たかい高いのはダメよ
- La viro laboras kun Sofia.
- 君
- Vi kaj mi ne loĝas en oficejo.
- de die diem
- Sofia estas virino.
- diem
- La virino ne dormas multe
- Sofia estas virino.
- in diem
- (데이터주의)자캐움짤 투척
- Adamo laboras multe.
- de
- gammel
- Adamo laboras multe.
- die
- Mi estas en la oficejo.
- Mi estas en la oficejo.
- de die in diem
- 神々